ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(中編・破)
前回は導入編として、研修の背景や目的についてお伝えしました。本編では、実際にどのようなイベントを実践したかをご紹介します。
前編はこちらの記事で紹介しています。
ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(前編・守)
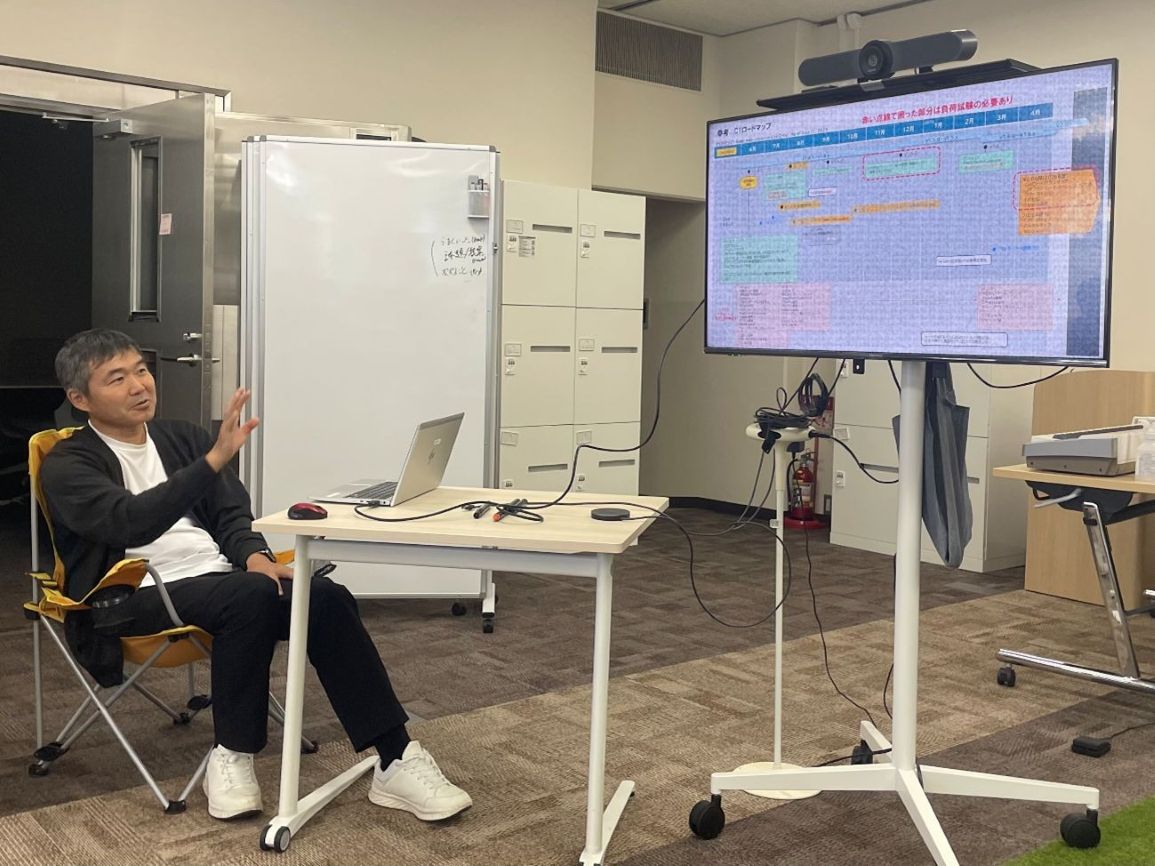 ■課題
■課題
まず、現状の課題を整理してみます。
・新製品の品質を保証する必要がある
・しかし、新製品に関して十分に理解できない部分がある
・情報や知見が一部のメンバーや部署に偏っている
この課題を解消するためには、
・新製品を理解しているメンバーや部署が知見を共有する
・暗黙知を集合知として昇華する
ことが必要です。もちろん、自らファーストペンギンになって、「わからない」を「見える化」する姿勢も重要です。
■ナレッジ返杯
まず最初に ”ナレッジ返杯(前回ブログをご参照下さい)” をしていただいたのは、新製品の受け入れテストを担うプロダクトオーナーユニット(以下、POU2)のみなさん。システム構成からテスト環境の構築方法まで、丁寧に解説をして頂きました。質問もたくさん出て、双方向に活発なコミュニケーションが生まれました。
返杯を受けたからには、ナレッジを飲み干して(吸収して)、こちらのナレッジを注いて返す必要があります。というわけで、自動E2Eテストユニット(以下、UAE)からは、新製品に関するアーキテクチャー図/シーケンス図の説明、負荷検証の話など、グラスなみなみにナレッジを注いて返しました。
 続いて、品質保証ユニット(以下、QAU)との合同ふりかえり会を実施。Keep/Problem/Try(KPT)のフレームワークを通して、各チームの目標の達成度を確認し、流動的なコミュニケーションから連鎖的な知見共有が展開されました。
続いて、品質保証ユニット(以下、QAU)との合同ふりかえり会を実施。Keep/Problem/Try(KPT)のフレームワークを通して、各チームの目標の達成度を確認し、流動的なコミュニケーションから連鎖的な知見共有が展開されました。
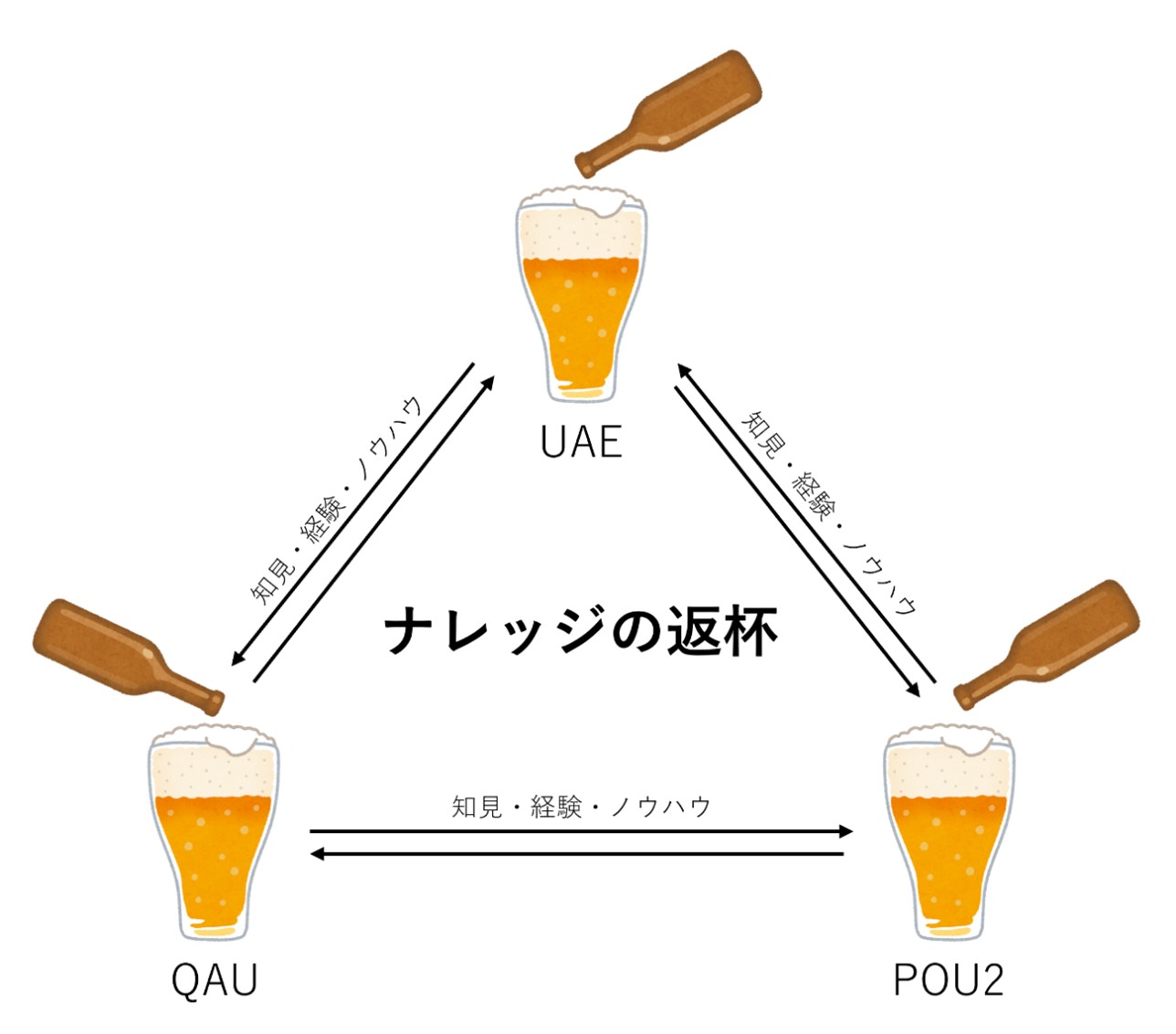 このように、合宿型研修では部署の垣根を越えた知見の交換・循環が実現しました。
このように、合宿型研修では部署の垣根を越えた知見の交換・循環が実現しました。
・POU2 → UAE/QAU → POU2
・UAE ⇄ QAU ⇄ UAE
返杯を比喩とした”ナレッジクロスオーバー”が形となった瞬間です。
次回、研修まとめ編。サービス、サービスゥ♪
前編はこちらの記事で紹介しています。
ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(前編・守)
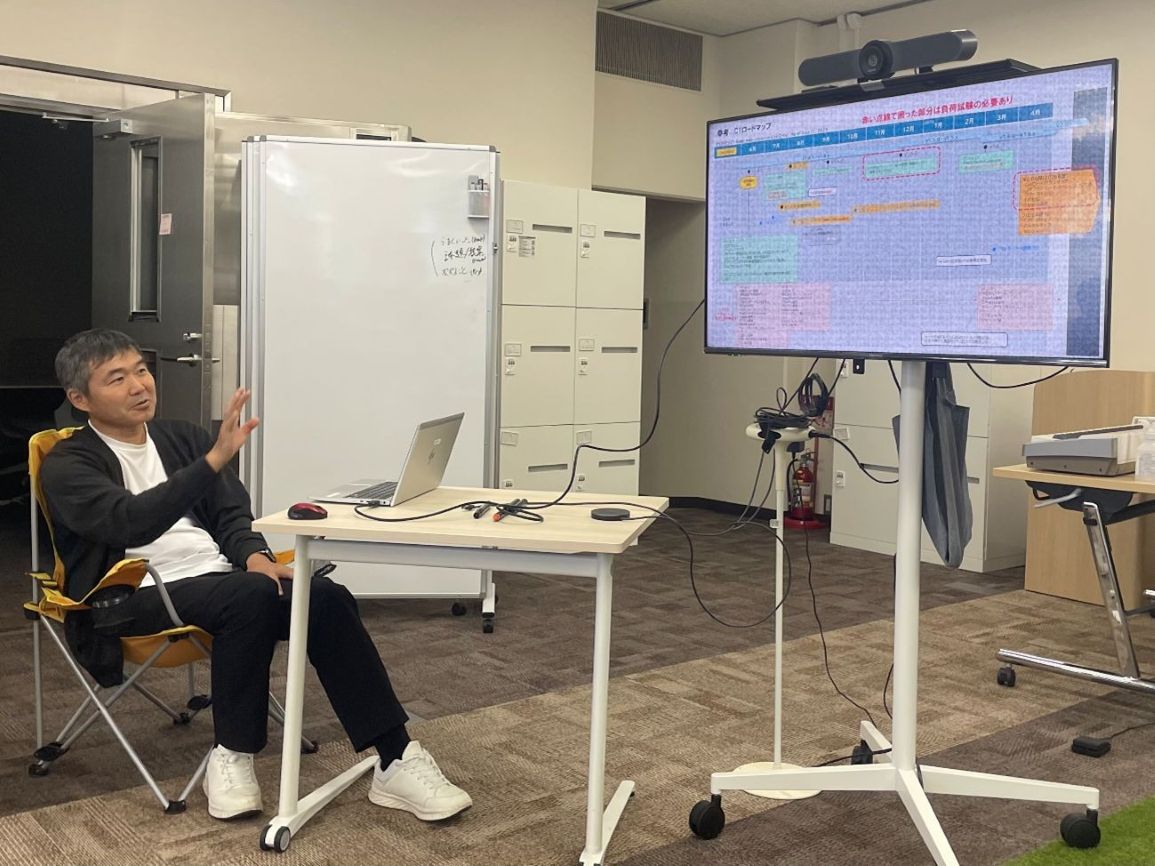
まず、現状の課題を整理してみます。
・新製品の品質を保証する必要がある
・しかし、新製品に関して十分に理解できない部分がある
・情報や知見が一部のメンバーや部署に偏っている
この課題を解消するためには、
・新製品を理解しているメンバーや部署が知見を共有する
・暗黙知を集合知として昇華する
ことが必要です。もちろん、自らファーストペンギンになって、「わからない」を「見える化」する姿勢も重要です。
■ナレッジ返杯
まず最初に ”ナレッジ返杯(前回ブログをご参照下さい)” をしていただいたのは、新製品の受け入れテストを担うプロダクトオーナーユニット(以下、POU2)のみなさん。システム構成からテスト環境の構築方法まで、丁寧に解説をして頂きました。質問もたくさん出て、双方向に活発なコミュニケーションが生まれました。
返杯を受けたからには、ナレッジを飲み干して(吸収して)、こちらのナレッジを注いて返す必要があります。というわけで、自動E2Eテストユニット(以下、UAE)からは、新製品に関するアーキテクチャー図/シーケンス図の説明、負荷検証の話など、グラスなみなみにナレッジを注いて返しました。

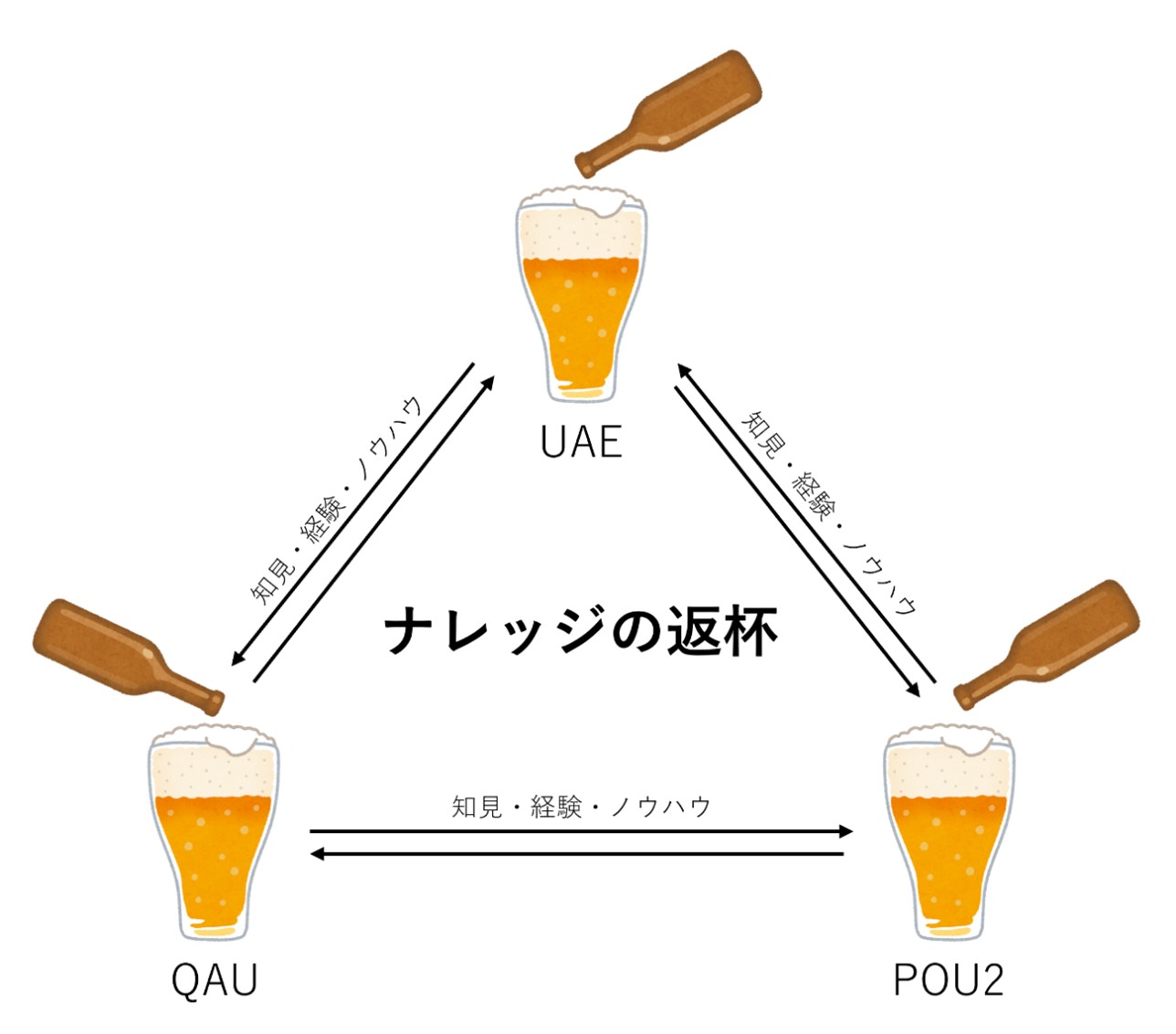
・POU2 → UAE/QAU → POU2
・UAE ⇄ QAU ⇄ UAE
返杯を比喩とした”ナレッジクロスオーバー”が形となった瞬間です。
次回、研修まとめ編。サービス、サービスゥ♪











